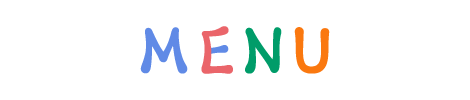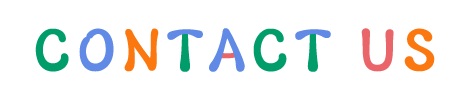事例・実績
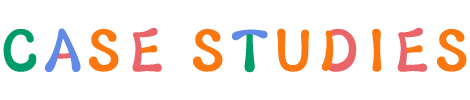
これまでにも、多くのお客様に選ばれています。
ここでは過去に施術を行ったケースをご紹介します。

- 脳梗塞後遺症の事例
-
広島市安佐南区(72歳・男性)
2024年1月脳梗塞の後遺症による右半身の強い痛み、しびれ、麻痺のため日常生活に支障があったが、訪問鍼灸マッサージを数ヶ月受けた結果、痛みが和らぎ、しびれや麻痺が軽減し、以前よりスムーズに体を動かせるようになった。
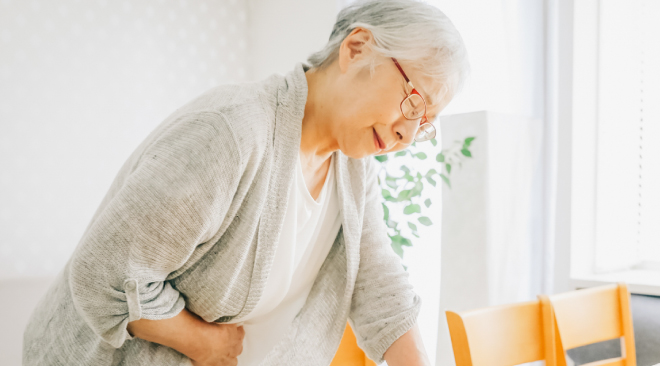
- 脳梗塞後遺症の事例
-
広島市安佐南区(72歳・男性)
2024年1月脳梗塞の後遺症による右半身の強い痛み、しびれ、麻痺のため日常生活に支障があったが、訪問鍼灸マッサージを数ヶ月受けた結果、痛みが和らぎ、しびれや麻痺が軽減し、以前よりスムーズに体を動かせるようになった。

- 床ずれの事例
-
広島市西区(78歳・男性)
2022年2月寝たきりの状態が長く、床ずれがひどくて、痛みでほとんどの時間横になっている状態でしたが、訪問介護を利用するようになり、丁寧な体位変換や褥瘡ケアのおかげで、床ずれの状態が徐々に改善してきました。今では痛みが和らぎ本当に嬉しいです。

- 肩こりの事例
-
広島市安佐南区(55歳・男性)
2024年1月長年のデスクワークによるひどい肩こりに悩んでいましたが、マッサージに通う時間がない中、訪問鍼灸を試したところ、自宅でリラックスして施術を受けられ、施術後には肩と首の痛みが軽減し、仕事に集中できるようになりました。

- リハビリ不足の事例
-
廿日市市(62歳・女性)
2021年2月骨折後のリハビリ不足で関節が固まり、日常生活に苦痛を感じていました。機能訓練プログラムを受け、理学療法士の丁寧な指導により関節の可動域が広がり、スムーズに動けるようになり、趣味のガーデニングを楽しめるようになりました。
- 腰痛症
-
- □ 腰椎椎間板ヘルニア
- □ 腰部脊柱管狭窄
- □ 圧迫骨折
【腰痛症】
昔から腰痛になる原因は数多くあるため、現代においても原因のはっきりわからない腰痛が多くを占めます。そのため腰が痛ければ全て腰痛症という症状に分別されます。
代表的なものは椎間板(ついかんばん)ヘルニア、腰部脊柱管狭窄(ようぶ せきちゅうかん きょうさく)、圧迫骨折といったものがあります。
腰痛は姿勢の悪さや生活における心身の影響、神経障害といった直接的な原因の他にもがんや細菌感染によって引き起こされたりもします。
体(身体的影響):長時間同じ姿勢でいる仕事、運動不足、肥満、冷え性など
心(精神的影響):職場や家庭でのストレス、不安、不眠など腰部椎間板ヘルニア
(ようぶ ついかんばん へるにあ)椎間板は背骨をつなぐクッションの役割を持っています。その一部が後方へ出てしまうことで神経が圧迫されてしまいます。 発症すると腰痛と共に、下肢のしびれや痛みによって歩きにくくなります。
腰部脊柱管狭窄
(ようぶ せきちゅうかん きょうさく)脊柱管(せきちゅうかん)という、脊椎にある神経を囲んでいる管が狭くなってしまうことで神経を圧迫してしまいます。
歩き続けると下肢への痺れや痛みが発生する間欠跛行(かんけつ はこう)という症状に見舞われます。圧迫骨折
(あっぱく こっせつ)中高年に多い、比較的頻度の高い骨折の一種で、椎骨(脊椎を構成する骨)が骨粗鬆症(こつそそうしょう)や感染症などで弱まっていたり、外部からの圧力(尻餅や転倒など)によって発症します。
骨折した部位に強い痛みを伴い、筋力の低下や知覚麻痺といった症状を起こすこともあります。
- 脳卒中
-
- □ 脳梗塞
- □ 脳出血
- □ くも膜下出血
【脳卒中】
脳の血管が詰まってしまったり、破れてしまうことで脳細胞が破壊され、脳が正常に機能しなくなることを脳卒中といいます。
脳卒中にはいくつかの種類があり、大きく脳梗塞(のう こうそく)、脳出血、くも膜下出血に分けられます。
これらの症状は治療を行っても後遺症によって、身体部位の麻痺などの機能障害が起こる可能性があるため長期のリハビリが必要になります。脳梗塞(のう こうそく)脳に栄養や酸素を運ぶための血管が閉じてしまったり、狭くなってしまうことで、十分な供給がされず脳組織が壊死、またはそれに近い状態になることを言います。
発症すると神経麻痺や言語障害、感覚障害などの症状が現れ、治療後も後遺症によって麻痺などの機能障害を筆頭に、多くの障害が残る可能性があります。脳出血(のう しゅっけつ)脳内血管が破れてしまい脳の中で出血してしまうことを言います。
主な原因は高血圧によるもので、意識障害や運動麻痺、感覚障害などの症状が現れ、後遺症も同様のものが示されます。くも膜下出血(くもまくか しゅっけつ)脳を覆うくも膜の内側、脳脊髄液(のうせきずいえき)という液体部分に出血してしまうのがくも膜下出血です。
突然強烈な頭痛に起こり、同時に吐き気や嘔吐などの症状が起きます。
後遺症は発生した部位によって異なりますが、代表的なものは運動神経の妨げによって起こる片麻痺です。
- 脊髄小脳変性症
-
- □ 孤発性
- □ 遺伝性
【脊髄小脳変性症】
歩いた際にふらついたり、手の震えやろれつが回らないといった運動失調が主な、神経疾患の総称を脊髄小脳変性症(せきずい しょうのう へんせいしょう)といいます。主に脳から脊髄にかけての神経細胞が少しずつ破壊、消失していくもので、病型を大別すると孤発性(非遺伝性)と遺伝性の2つに分けられます。 運動失調の他にも自律神経障害を起こすもので、日常生活を送るためにもケアが必要になります。孤発性(こはつせい)孤発性は中でも大きく多系統萎縮症、孤発型皮質小脳変性症、及びその他の症候性小脳変性症に分類されるもので、日本人の中ではもっとも多い病型です。初期症状としてはふらつきなどの運動失調から、経過とともに様々な障害に見舞われます。
特に自律神経障害の症状がでるようになりますと、日常的な生活に支障がでるため介護やサポートが必要になることも少なくありません。遺伝性(いでんせい)原因遺伝子によって数多く分類される脊髄小脳変性症で、その分類によって起きる症状も様々です。
基本的には孤発性のものと同じような症状に見舞われますが、それに加え足がつっぱってしまう錐体路症状や、眼球が勝手に動く眼振といったものなど、症状からの影響がより顕著になります。そのため症状ごとに適切な治療法とリハビリが必要となります。
- パーキンソン病
-
- □ 本態性
- □ 二次性
- □ 症候性
パーキンソン病
パーキンソン症候群はパーキンソン病という神経変性疾患、およびその症状に呈する総称です。
中年から高齢になるほどその発症の割合も多くなるこの症状は、主に静止時振戦(せいしじしんせん)と呼称される、じっとしているときに発生する手足の震えや動きが緩慢になる無動、筋肉が固くなりスムーズに動けなくなる筋強剛、体の姿勢を整えづらくなる姿勢保持反射障害が挙げられます。
分類は大きく分けて、本態性、二次性、症候性の3つになります。本態性(ほんたいせい)主なパーキンソン病の分類は本態性になります。
前述の静止時振戦、無動、筋強剛、姿勢保持反射障害が主ですが、その他にも自律神経障害やうつ病、認知症を伴う場合もあります。
進行すると運動が困難になりますが、そのまま運動をしなければ筋力低下につながりますので運動によるリハビリが推奨されます。二次性(にじせい)前述の本態性とは別にそれ以外の神経変性疾患でパーキンソン病を伴うものを言います。
脳変性疾患と併発するものが多く、前述の本態性の症状が加わり、またそれに似た症状が発症することで生活が困難になる場合もあります。症候性(しょうこうせい)本態性、二次性による変性・代謝異常以外の疾患によってパーキンソン症候群となるケースです。
薬物性や中毒性のものから心因性といったものまで、多くの要因が考えられるため、治療方法も様々となります。
- 寝たきり
-
- □ 衰弱
- □ 骨折
- □ 痴呆
- □ 関節疾患
- □ 心臓病
寝たきり
寝たきりに明確な定義はありません。しかしその状況に至る原因は衰弱や骨折、痴呆といった日常生活に支障のある症状から、やむを得ずして動くことのできない、横にならなければならないことになってしまいます。衰弱(すいじゃく)病気や老化によって、筋力の衰えや歩行速度の低下、活動量の低下、疲労の蓄積、体重が減ってしまうことを言います。
健全な生活を送れない場合、身体の不使用によってより弊害が強まってしまうため、生活環境の見直しや介護が必要となります。骨折(こっせつ)一般的には外力によって身体を構成する骨が変形、破壊を起こす外傷のことを言います。骨折はその状態により様々な分類がされますが、どれも痛みや腫れを引き起こすもので軽度のものでも行動に制限がかかるようになります。
治療には時間を要し、治療後も筋力の低下に見舞われるため、リハビリにも注意が必要になります。痴呆(ちほう)脳疾患による症状で、物忘れが多くなる記憶障害、言葉の出ない失語、上手く行動ができない失行、認識ができない失認、予定や計画を立てれなくなる実行機能の障害が挙げられます。
どの症状をとっても日常生活に支障をきたすものであり、完全に治すことも難しく、薬物療法とリハビリテーションによって症状を軽くしたり、進行を抑えていくようになります。関節疾患(かんせつ しっかん)身体を構成する骨は多くの関節によってつながれています。その関節が何らかの原因で異常をきたすと、動いた際に痛みが起き、日常生活にも支障がでます。
関節にある軟骨は自然治癒力も低く、放っておいても回復しづらいものです。そのため関節疾患は、ひとりひとりに合わせた治療が重要で、症状を自覚した場合、早めに医師に診断してもらい、ケアを続けていかなければなりません。心臓病(しんぞうびょう)心臓疾患の総称で心疾患とも呼ばれます。心臓は重要性の高い臓器のため、症状も重篤になるケースが多いとされます。
心臓病には数多くの症状がありますが、主には胸痛や動悸といったものが挙げられ、重くなると一時的に行動ができなくこともあります。運動に大きな制限がかかることも少なくないため、そのまま寝たきりになってしまう人もいますが、それから筋力の衰えやストレスによって別の症状が起きる可能性もありますので、適切な介助やコミュニケーションが必要です。